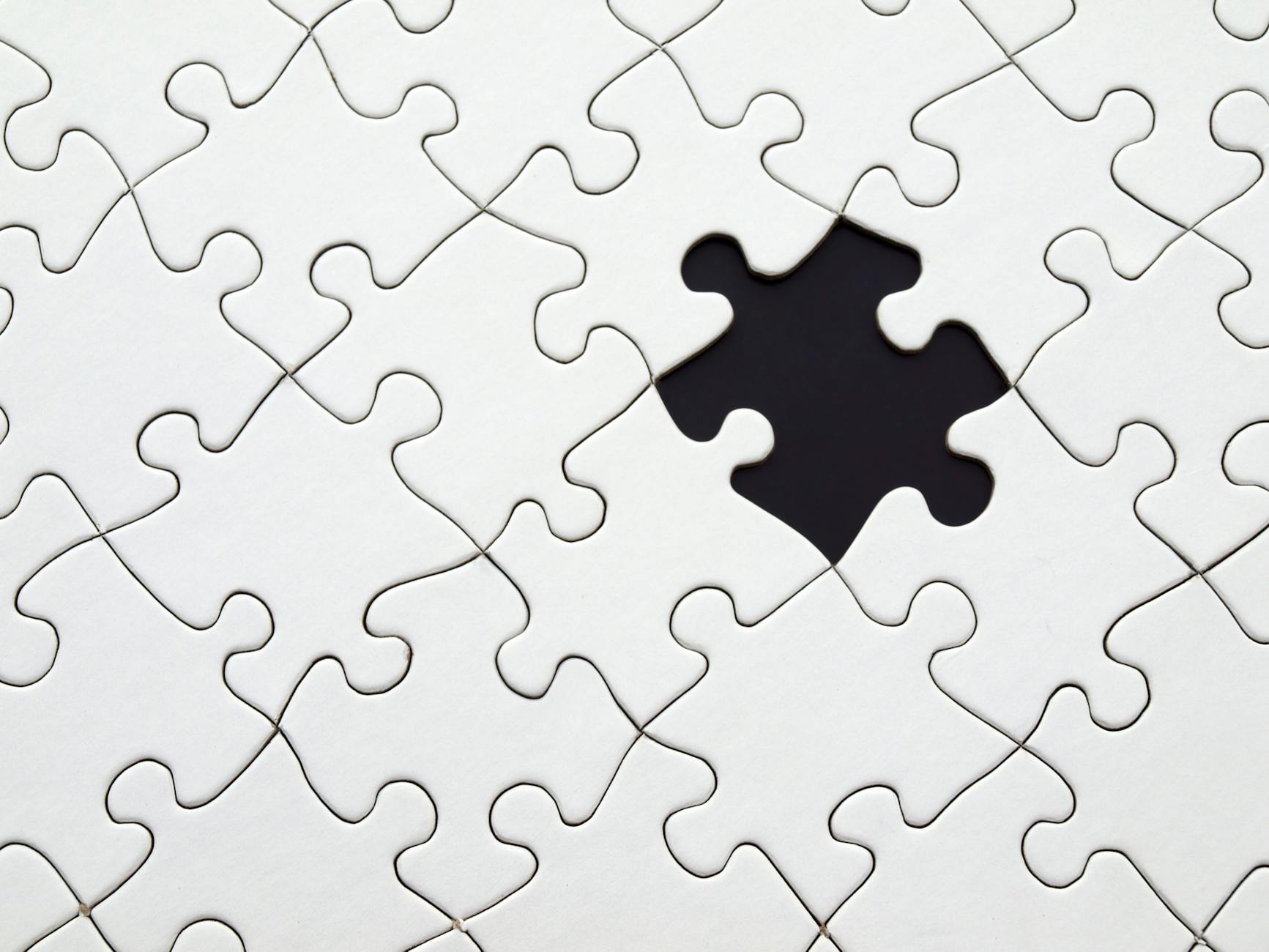リハビリテーションの現場で、私たちは日々「動作分析」を行っています。しかし、多くの若手セラピストが「どこが悪いかはなんとなく分かるけれど、なぜそうなっているのか、どう変えればいいのかが分からない」という壁に突き当たります。
今日は、スタッフとのケーススタディを通じて再確認した、患者さんが動作に失敗している「本当の問題フェーズ」を見抜くコツについて、詳しくお話ししようと思います。
1. 重心の軌跡が教えてくれること
以前のブログでもお伝えしましたが、動作分析において最も重要な指標の一つが「重心の移動」です。立ち上がり動作であれば、座面から離れる(離殿)までに重心がスムーズに前方へ、そして上方へと移動していく必要があります。
重心の動きを観察していると、以下のような現象に気づくはずです。
• ある一点で重心の移動がピタッと止まってしまう。
• 重心が本来通るべき軌跡から外れ、変なカーブを描いてしまう。
• 上方へ上がるべきところで、逆に重心が下がってしまう。
これらはすべて、そのフェーズで動作が「失敗」しているサインです。しかし、場所を見つけただけで満足してはいけません。大切なのは、「なぜそこで重心移動ができなくなってしまうのか」という背景にある力学的な、あるいは神経学的な理由を探ることです。
2. 視点の転換:「動きすぎ」と「動かなすぎ」を探す
原因を探る際、私は常に「動きすぎている場所」と「動かなすぎている場所」の対比を意識しています。
人間の体は、どこかが動かなければ、他のどこかがそれを補おうとします(代償動作)。セラピストの目は、どうしても派手に動いている場所や、ガチガチに固まっている場所に奪われがちですが、実はその裏に隠れた「全く動いていない静かな場所」こそが、諸悪の根源であることが多いのです。
今日、スタッフと一緒に担当した60代女性の脊髄梗塞の患者さんの実例を挙げて解説しましょう。
【症例プロフィール】
• 疾患: 脊髄梗塞(胸髄レベル)
• 基本動作(立ち上がり): 平行棒や手すりがあれば自力で起立可能。ただし、離殿時に過剰な努力を要し、膝折れの不安がある。
• 立位姿勢: 手すりを強く引っ張ることで立ち上がり、股関節が屈曲、腰椎が過剰に伸展、反張膝(バックニー)気味となる。立位姿勢は骨盤は過剰に前傾し、脊柱は代償的に伸展している。
• 身体機能: 随意運動(分離運動)は比較的良好で、足・膝・股関節の自動運動は可能。ただし筋力低下があり、特に左下肢のMMTは2レベル(右は3〜4)である。また感覚障害は軽度。
【現場での葛藤】
スタッフが悩んでいたのは、立ち上がりの誘導時の「抵抗感」でした。
「患者さんの上半身を前方へ誘導しようとすると、体が突っ張ってしまって重心が前に進まない。骨盤が後ろに取り残されたような感じがするんです」
実際に触れてみると、確かに股関節の屈筋群(特に大腿直筋の近位部)が過剰に張っており、誘導を拒むような強い収縮が見られました。このような症例をみなさんも一度は経験したことがあると思います。
3. 「真の問題点」はどこなのか?
一緒に介入したスタッフは、この「股関節屈筋の過剰な活動」を問題視しました。
「ここが硬いから重心が前にいかないんだ。だから、まずはこの屈筋群を緩めて、代わりに大臀筋が働くようにトレーニングしよう」
これは一見、理にかなったプランです。しかし、実際に筋肉をほぐし、筋力トレーニングを行っても、立ち上がりの動作のパフォーマンスはなかなか変わりませんでした。
ここで私は、あることに注目しました。
「この人の体の中で、一番仕事をしていないのはどこだろう?」
観察を深めると、驚くほど「胸椎」が動いていないことに気づきました。通常、立ち上がりで前傾していく際には、胸椎の適切な伸展や回旋の微調整が必要ですが、この患者さんの背中は一枚の板のように固まっていたのです。
背景にある既往歴
ここで重要なのが、疾患の背景です。ご存知の通り、脊髄梗塞は、大動脈解離の手術に伴って発症することが多々あります。この患者さんも胸骨を切開する大きな手術を経験されていました。
手術による組織の癒着、術後の痛みによる固定、そして脊髄損傷による神経伝達の阻害。これらが重なり、胸椎周辺の可動性が完全に失われていたのです。
4. 介入のプロセス:動かない場所に「油」を差す
方針を大きく変え、私たちは「胸椎の可動性」に徹底的にアプローチしました。
1. 胸椎のモビライゼーション:
セラピストが後方に位置し、背もたれに寄りかかるような姿勢になり胸椎の屈曲・伸展・回旋・側屈を引き出しました。最初は全く動く気配がありませんでしたが、二人がかりで丁寧に、リズムよく運動性を求めていくと、徐々に脊柱の運動性が戻ってきました。
2. 連鎖的な変化:
胸椎が動き出した直後、驚くべき変化が起きました。あれほどガチガチだった股関節屈筋の過剰な収縮が、何も触れていないのにスッと抜けたのです。骨盤の前後傾がスムーズになり、上半身を前に誘導した時の抵抗感も消失しました。
3. パターンの再学習(ここが最重要!):
抵抗がなくなっただけでは不十分です。患者さんの脳は「股関節を固めて立つ」というパターンを覚えています(これを誤学習と言います)。
ここで初めて、股関節屈筋を過剰に使わずに、大臀筋やハムストリングスを収縮させる練習に移行します。股関節が屈曲位にならないよう注意しながら、高座位(少し高くした座面)から立ち上がる練習を繰り返し、正常に近い筋収縮の順序(運動パターン)を脳に書き込んでいきました。正しい運動を繰り返すことで効率的な運動の再学習を促進します。
結果としての変化
最終的に、立位での姿勢は見違えるほど変わりました。いつも引けていた腰がスッと伸び、脊柱の過度な反りも軽減。触れるとガチガチだった腰部の筋肉も柔らかくなっていました。
5. 臨床を「間違い探し」として楽しむ
今回のケースで学べるのは、「目に見える過剰な緊張は、どこかの不活動の裏返しである」ということです。
セラピストは、介助のためにどうしても患者さんに密着してしまいます。近すぎると全体像が見えなくなり、「硬いところを揉む」という局所的な思考に陥りやすくなります。
転倒に注意しながらも、時には少し離れた位置から眺めてみてください。あるいは、触れている手を通して「どこがサボっているか」を探り当ててください。
動かない場所を見つけ、そこに適切な刺激を与えた時、全身がまるで油を差した機械のように滑らかに動き出す瞬間があります。これを私たちは「運動連鎖」と呼びます。この連鎖が繋がった瞬間、リハビリは単なる「訓練」から「感動的な体験」に変わります。
私はよく、この作業を「間違い探し」のゲームのようだと言います。
「どこが動いていないのかな?」「ここが動いたらどう変わるかな?」
患者さんと一緒に、失敗を恐れずにこのプロセスを楽しむこと。
「あ、ここが硬いですね」「ここを動かすと楽に立てますね」
そんな風に対話しながら進めるリハビリは、患者さんにとっても主体的な発見の場になります。そして自分が狙った部分から全身に変化を与えることができた時のよろこびは何にも変え難い喜びになります。
6. 明日から実践できるステップ
このブログを読み終えたら、ぜひ明日の臨床で一人、特定の患者さんに絞って以下のステップを試してみてください。
1. 観察: 動作のどこで重心が止まるかを見つける。
2. 抽出: その時「動きすぎている場所」と「全く動いていない場所」をリストアップする。
3. 仮説: 「動いていない場所」が動けば、「動きすぎている場所」は休めるのではないか?と考える。
4. 検証: 動いていない場所に可動性を出し、もう一度同じ動作を行ってみる。
リハビリの時間(40分や60分)は、この仮説検証を何度も繰り返すための時間です。20分アプローチして変化がなければ、次の仮説へ、を繰り返せば一セッションで2、3回も試行錯誤できます。本当の問題点さえ見つかれば、あとはアプローチするだけです。
「本当の原因」を見つけた時、セラピストの技術は最大限に発揮されます。なんなら、原因がわかれば患者さん自身やご家族に「ここを意識して動かしてくださいね」と伝えるだけで、劇的な改善を維持できることさえあります。
患者さんと共に「動きの謎解き」を楽しんでください。その先にある、スムーズで軽やかな動きを手に入れた時の患者さんの笑顔は、何物にも代えがたい報酬になるはずです。
【終わりに】
今回の脊髄梗塞のケースのように、既往歴や手術痕が現在の動きを縛っていることは非常に多いです。「病名」を見るだけでなく、その方の「体の歴史」を紐解くことで、動かない場所のヒントが見えてくるかもしれません。ここに現病歴だけではなく既往歴や合併症などをカルテからしっかり読んで、理解する意味があるわけです。
もし、この記事を読んで「自分の担当患者さんのこの動きはどう考えればいい?」という疑問が湧いた方は、ぜひコメントやメッセージをください。一緒に「間違い探し」を深めていきましょう。