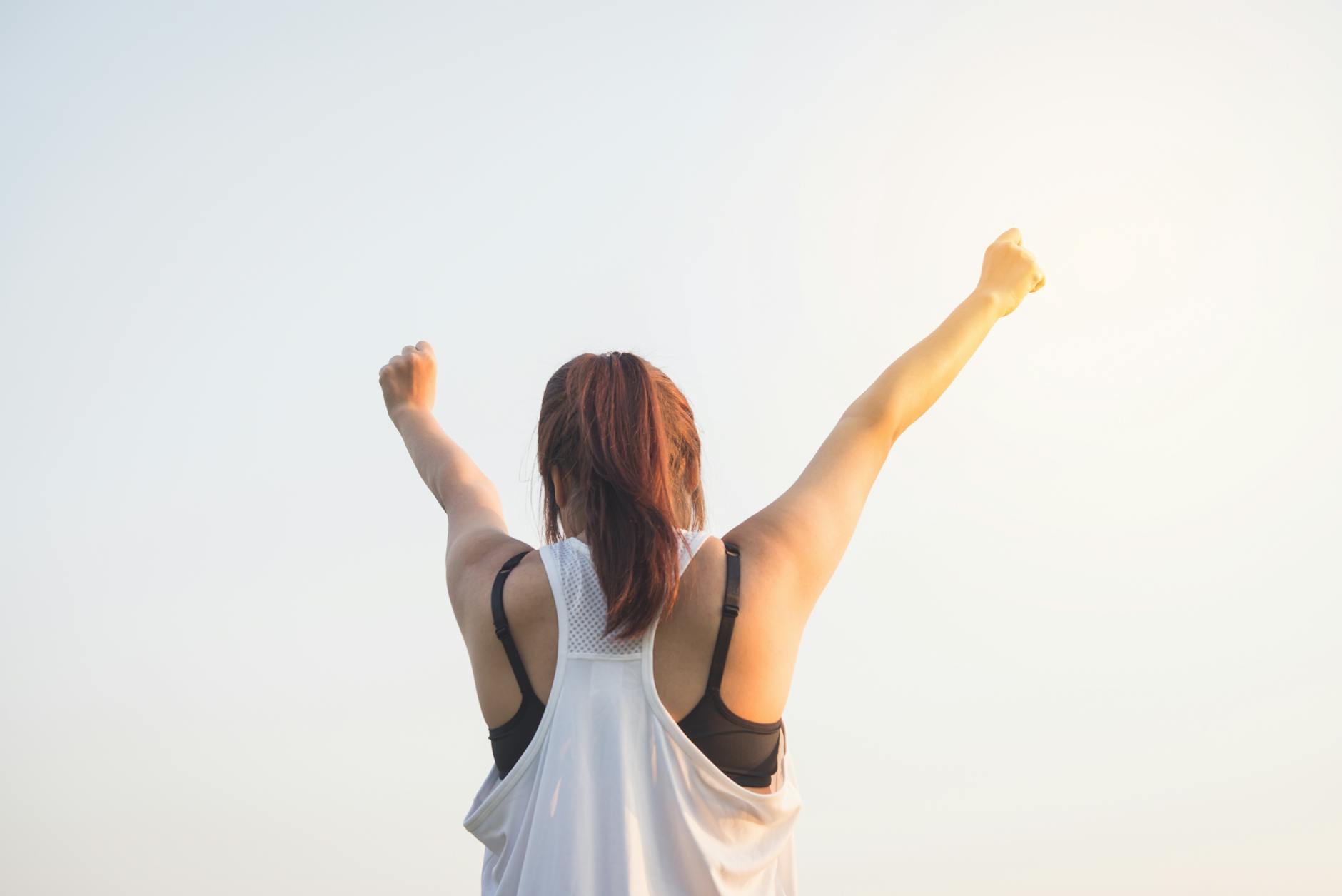リハビリ職が70人を超えた回リハ病院ともなると、スタッフの中には精神的に病んで職場に来られなくなるスタッフも少なくはありません。働き方改革の影響もあり、スタッフの業務負担は10年ほど前に比べるとかなり少なくなりました。そのおかげで改革前後では、心の病のために休職や退職をするスタッフはかなり減りましたが、それでも全くなくなったわけではありません。その都度管理職として病んでしまった彼らに対応するわけですが、しばしば彼らからは「自分は、他の人よりも仕事ができない。辛い。周りに比べて劣っている気がする。」というような言葉が聞かれます。多くの場合は本人たちが言うほど仕事ができないということはありません。むしろ他の人よりも頑張っているように見えます。しかし実際に彼らはそう感じてしまっているのが事実です。もしかしたら辞めずに仕事を続けているスタッフの中にも同じ悩みを抱えて悶々としている人もいるかもしれません。皆さんも一度は同じような悩みを持たれたことがあるのではないでしょうか。私も20代後半くらいの時に、自分より評価されている部下に対して同じ感情を持ったことがありました。自分と他人を比べてしまう辛さ、それなのに解決できない自分を責める気持ちははよくわかります。
どうして人は他人と自分を比べてしまうのでしょう。私たちは子供の頃から順位をつけられてきました。運動会のかけっこで1番を決めたり、学力テストで学年で何番かを張り出されたり。この教育システムに問題があるのでは、といろんな情報誌で目にします。それに応じてなのか運動会でも順位をつけない学校もあるとのこと。ちなみにうちの地元の小学校はしっかり順位をつけています。私の考えはというと、私はこのシステム自体は肯定も否定もありません。順位が無ければ自分が他人と比べて何が得意で不得意かわからないし、順位が上がったり下がったりして自分の成長や伸び悩みなどを感じることができません。そういう側面においてはメリットはとても大きいと感じると思います。しかしいくつかの結果だけでその人の優劣を決めつけたりするのはあまりよくないと思うのは私だけではないでしょう。昔から言われ続けてきたフレーズですが、「誰にでも他人よりも好きなことや得意なことが必ずある」と言うのは本当だと思います。
心が弱ってしまい、仕事に行かれない人たちに話を戻します。仕事ができないとか、仕事に行きたくないという心持ちになる根本の原因には、「自分自身のことをよく知らないのでは?」と最近思います。誰がなんと言おうと私はこれが得意、または得意でなくても好き、人よりも長く継続できる、というものがあるかどうかが大切です。そしてそれを誰かに評価されようと思わないことです。もとより好きなことなので他の人の評価への期待が入る余地は少ないとは思いますが。
そして、個人から環境に話を移すと、もっと社会全体が人の評価尺度をたくさん持つといいのでは、と思います。私が入職してからの10年近くは、理学療法士として臨床力があることだけが評価尺度でした。そのためそれに価値を見出せない人たちはたくさん辞めていきましたが、奇しくも若かった私も臨床が全てだと勘違いし、病院の間違った方向性に完全に乗っていた人間だったので辞める事はありませんでした。臨床力といっても、それを可視化できるものはなく、なんとなく臨床に向かって頑張っている、勉強会によく参加しているなどという漠然とした客観的なイメージだけで評価されていもいたと思います。そのため実際の臨床ではぼーっとして、本気で患者さんに向かい合っているとは言えない人が、実技練習や勉強会になると途端に活き活きする人も多く、支離滅裂な評価しかありませんでした。多くの人が退職するのも無理はありません。しかし辞めた方々の中にも、心理的に患者さんをサポートできる人、プログラミングが得意で仕事の効率化に長けていた人、情熱があって周りの人のモチベーションを高めることができる人、たくさんいました。それぞれが職場に対して有益な長所を持っていたはずです。その組織への貢献に対して会社が適切な評価をせず、そのためにその人たちも自分の長所に気づくことができないのはとてももったいないことだと思います。もっとそれぞれの長所を活かした仕事を任せてやらせてみることが大切ではないでしょうか。
そこで、それぞれの良いところがあっても全ての人が昇格や昇給するわけじゃない、モチベーションが維持できないのでは、と言う問題が出てくると思います。そこは管理職の仕事です。それぞれのスタッフに適したインセンティブを与え、高いモチベーションを維持するしかありません。個人的には医療系の仕事をしている人は金銭的インセンティブよりも人的インセンティブや自己実現インセンティブを期待する人も少なくないと思います。彼らの見えない仕事をつぶさに見つけ、承認していくことだけだと思います。人の目につきにくい部分を褒められるのはとても嬉しいものですし、そもそも得意なことというのはその当事者が無意識にやっていることも多いので、こちらから「あなたの得意分野」を伝えてあげることもその人が自身の強みに気づけるチャンスになります。
それぞれのスタッフが自分の強みを見つけられる。ここは自分の力が発揮できるけど、ここは苦手だから優れた他の人に頼もう、で仕事は問題なく回ります。そんな心持ちで働けば、他人と自分を比べて不毛に悩んで、心をすり減らし、本来であれば自分の力を存分に発揮できるはずだった仕事を辞めなければならないという境遇を少なくすることができるのではないでしょうか。
少しでもそんな社会に近づけられるように、と言う願いを込めて今回の記事を締めたいと思います。